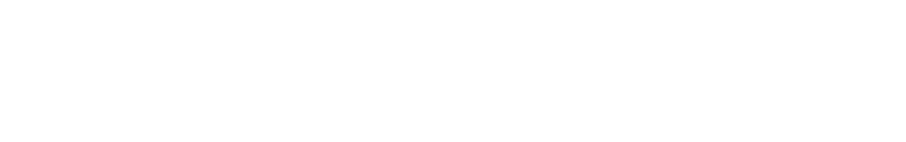善了寺のなりたち
当寺は大島山宝林院善了寺と申し、浄土真宗本願寺派の寺院です。
元来は真言宗で、和泉村(現在の泉区和泉町5291番地 現在正法寺のあるところ)に在りましたが、「親鸞聖人」60歳の天福元年(1233年)、江戸麻布・善福寺の釈了海の弟子「釈了全」により、浄土真宗に改められました。
ゆえに、釈了全を開山としています。釈了全は弘安8年(1278年)3月5日に往生されました。
その後領主の強制により浄土宗に改宗を命ぜられ、大部分の檀家は改宗しましたが篤信の門徒(現在の戸塚区深谷町・影取町、瀬谷区宮沢町、泉区上飯田町、緑区白山町)によって細々と維持され、名ばかりの寺院でした。
今から約400年ほど前の天正年間に、さびれた善了寺を再興したのは「釈了唯」(号洞庵)で、当寺の中興と伝えられています。釈了唯は、俗名を「大久保加右衛門信唯」といい、武田信玄の家臣「大久保伊豆守秀唯」の子でありました。
信唯が晩年紀州に赴任したとき、「本願寺第11世顕如上人」(顕如上人は石山合戦の後、織田信長と和睦し鷺の森に在住しておられました)とお会いされ、法弟となり釈了唯と改め洞庵と号されました。
その後、家臣磯利嘉右衛門・嘉左衛門兄弟を召しつれて、当地に来て現在の場所に善了寺を移転され、衰退した善了寺を中興されました。
現在恒例の法要は 釈了唯が天正15年(1587年)4月8日に往生されたことにちなんで、8日に行っています。 『神奈川県皇国地誌 相模国鎌倉郡村誌』の「矢部町誌 寺」の項目(明治12年2月編成)には、「東西三十間南北二十間五尺四寸面積六百二十九坪本町東南ノ方ニアリ西京府下真宗西本願寺ノ末派ナリ天正年間僧洞庵開基創建ス」と記録されています。
正徳2年に梵鐘が鋳造されましたが、慶応3年10月12日(1866年)矢部町の大火によって、7間4面の堂々たる本堂、石坂右上の太子堂および庫裡は全焼し、鐘楼のみが残されただけになりました。その後、明治2年に本堂が再建されました。第14世釈智淳が明治23年に入寺したときは本堂だけで、そのほかは、何一つなかったと記録されています。その本堂も、大正12年(1923年)9月1日の関東大震災の時半壊しました。
旧本堂は、昭和20年(1945年)10月に 第16世 釈恵門によって再建されたものであります。昭和63年(1988年)釈了恵によって、ご本尊 阿弥陀如来立像の御修復がなされ、また、ご門徒の御懇念により親鸞聖人銅像の建立と、聖徳太子木像の修復を成し遂げました。
平成9年(1997)第18世釋智信が継職し、平成17年(2005)当寺庫裏にて通所介護事業「宗教法人善了寺 還る家ともに」を開設し、平成23年(2011)から平成28年(2016)まで親鸞聖人750回大遠忌法要記念事業として、東日本大震災復興支援事業とあわせて聞思堂建築・本堂・客殿・庫裏の新築事業を実施した。平成24年(2012)10月8日に、聞思堂落慶法要を勤め、平成25年(2013)に本堂はじめ諸施設の耐震調査を行い、調査結果を受けて、耐震化を重点項目として平成26年(2014)から本堂·客殿·庫裏の建築が始まり、平成28年(2016)10月8日落慶法要を勤める。
住職紹介
成田 智信(なりた とものぶ)
浄土真宗本願寺派 東京教区鎌倉組 善了寺 住職
宗教法人善了寺 代表役員
善了寺デイサービス還る家ともに 代表役員
本願寺講社 善了寺ともに講 担当者

皆さま、善了寺のホームページへようこそ。善了寺の住職 成田 智信(なりた とものぶ)と申します。この場をお借りして、お読みいただいている皆さまに感謝の意を表し、お寺の活動についてお伝えさせていただきたいと思います。
善了寺は、親鸞聖人にお伝え頂いた浄土真宗のみ教えを依りどころに、皆さんとご一緒に心豊かに生きることの出来る場所を目指して活動しています。お寺の門をくぐると、街の喧騒から離れ、静寂と慈しみの空間が広がります。阿弥陀如来の前で、日々のストレスや悩み、喜びや感謝を少しでも分かち合い、共に歩む場所として、善了寺をお考えいただければ有り難いです。
善了寺のホームページは、お寺の活動やイベント、お知らせなど、最新の情報を提供する場所としてお役立ていただければと思います。お問い合わせや訪問、お参りについての詳細な情報もご案内しておりますので、どうぞご自由にご覧いただき、お気軽にお寺へお越しいただければと思います。
最後に、私たち善了寺は、皆さまのお支えと共感に感謝しております。ご一緒に心静かに歩みを進め、善了寺での素晴らしい出遇いを共にしたいと思います。どんなときも、あなたの側にみほとけはともにおられ、善了寺があります。
心から、ご訪問と、共に学ぶ機会を楽しみにお待ちしております。
南無阿弥陀仏 合掌
善了寺 成田 智信(なりた とものぶ)
善了寺とつながろう!フォローして最新情報を受け取ろう
善了寺は、SNSを通じて善了寺の日常や仏教の教えについて配信をしています。
善了寺のメールマガジン
善了寺のメールマガジンでは、お寺の最新情報やスケジュール、特別イベントのお知らせ、そして、学びあるのエッセイなど、様々な内容をお届けいたします。
メールマガジンの購読は無料で、善了寺の活動に興味をお持ちの皆さまに、定期的にお寺の情報をお届けする手段としてご活用いただけます。私たちと一緒に、浄土真宗の教えを依りどころに、日常生活に仏教の教えを取り入れていきましょう。
メールマガジンへの登録は簡単です。以下のボタンをクリックして、ご自身のメールアドレスを登録していただくだけで、最新情報を手に入れることができます。善了寺のコミュニティにご参加いただき、一緒に学び、成長しましょう。
善了寺ニューズ
善了寺発信情報サイト
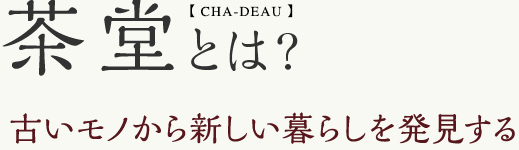
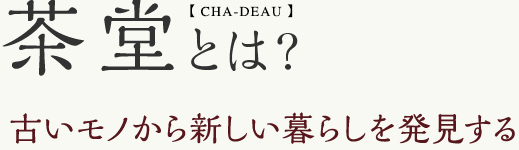
「茶堂」とは、かつて村の境や峠に設置された小さなお堂で、建物の三面に壁がなく、誰でも、どこからでも上がれるのが特徴です。
世代を問わず村民たちの憩いの場として使われていたほか、通りがかる旅人や商人たちが村人からお茶やお菓子のおもてなしを受け、旅の疲れを癒したといわれています。小さな交流の場が、時には先人から受け継がれた知恵を学び、時には異文化に刺激を受け共感し、日々の暮らしに取り入れるきっかけにもなっていました。そんな、ふらりと誰でも立ち寄れる茶堂のように、CHADEAUでは日本の伝統的な文化や暮らしのヒントを紹介し、現代に活かせるエッセンスを日々発信していきます。